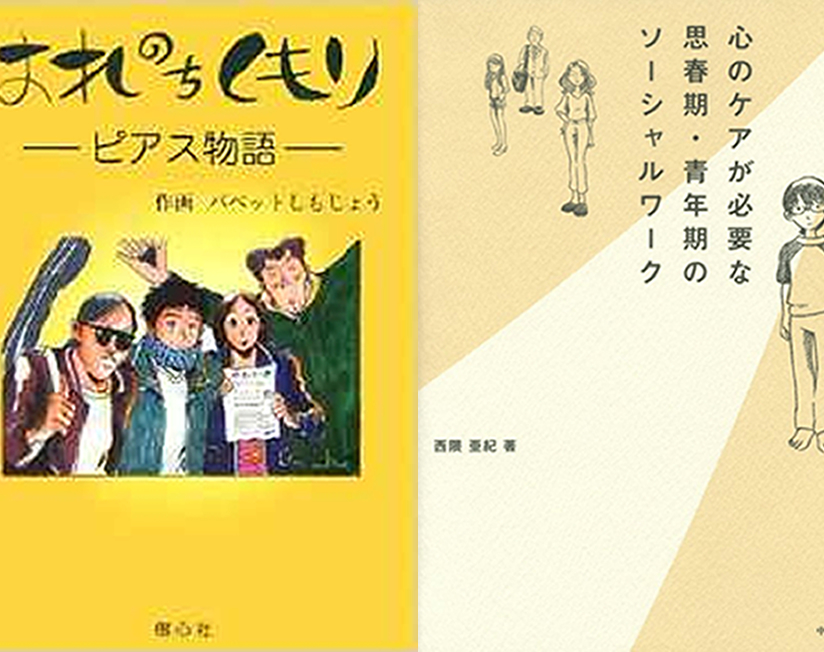対談編 – 小林由美子(棕櫚亭 理事長)✖︎ 櫻井 博(棕櫚亭 ピアスタッフ)
次世代につなげる、支援につなげる
あの頃見たことを語り続けることが必要だと思うようになった。様々な出来事が記憶の底に沈まないうちに、それを次世代の現在の仕事に繋げる事が私の役割かもしれない。
『精神障害のある人の就労定着支援 – 当事者の希望からうまれた技法』
天野聖子 著/多摩棕櫚亭協会 編著(中央法規出版) より
小林: 元職員の森内勝己さんを皮切りに『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』 (以下、『ある風景』)の後半戦も興味深く読ませていただきました。森内さんの文章が面白かったのは、棕櫚亭で仕事として体験したことが外に出てみて、深化しているというか。それは凄く分かりやすく書いてあって良かった。そして現在は福祉分野を離れてはいるが、今の仕事にきちんとつなげているのだと思いました。
櫻井: 経営感覚を磨くって凄いことですよね。目の前の支援をやりながらも、どうやってこの施設の行く先を考える、つまり森内さんで言えば広い視点で会社を経営しながらやっていく。ユニクロの社長が言っていたけど「全員が社長の気持ちでいないとダメだ」と話していたことを思い出しました。主体的に仕事に取り組みながら、俯瞰的にみていくことはこの世界にいると特に必要なことで、私なんか、ついいつのまにか目の前のことに巻き込まれています。
小林: 確かに柳井さん(ユニクロの社長)は強力な言葉をもっていますよね。あのレベルは難しいとしても、(精神障がい者の)支援を言葉で行なっていく私達、特に経営陣がまだまだ力量不足なのだと思う。勿論あれほど強烈にはなれないけど、言葉って大切で、私達もパートナーシップを持ちながらも、いろんな言葉を駆使して支援していくことは凄く大切だと思う。職員一人ひとり、みんながその意識をもってやってくれたら、凄い発進力になるよね。まず空気を読むということではなく。
話を戻しますが、『ある風景』の後半戦を読んで感じたのは、メンバー(利用者)に教えてもらったとかメンバーと共にやってきたとか、そういった精神みたいなものは今も棕櫚亭に大切に引き継がれているのは、この『ある風景』に一貫していると改めて感じました。多分、その具体的なものの一つはメンバーとのパートナーシップです。このパートナーシップというところは今も引き継がれて、それは利用者であるメンバーも今もとても評価してくれるところですよね。
と、同時にメンバーシップを大切にするような姿勢や精神といったものはきちんと私達が引き継ぐだけではなく、これからも先の世代に引き継いでいかなければいけないのだろうと思いました。
なぜ、こんなことを言うかというと前回(12月)の対談の終わりでも少し触れたとおり、引き継ぐということは、人を育てるということ、つまり人材育成のところに次の宿題が残されていて、連載のなかでもうひとつ大きなトライをしていかなければならないことだと改めて思いました。「人材育成」という単語こそ、職員が描く『ある風景』文章そのものには出てこないことなのだけれど、その意義について私自身として理解したということです。ともすると、人材育成のポイントは、もしかしたら今後研修なんかでケースワークの基本を学ぶことは勿論のこと、社会に対して広い視点をどうやってもてるようになるかと思ったりするわけですよ。
櫻井: 森内さんが言っていた「過去を振り返る」というところで「その起きたことは変えられないが出来事の意味は事後的に決まる、意思が未来を開き、未来が過去を意味づける」こういう言葉を最初に言って、結構センセーショナルな内容だなと思ったんですけど。
小林さんは「パートナーシップ」だけではこの社会福祉というものを乗り切れないということつまり、僕らは一歩すすんで天野さんが耕してきたことをもう一回考え直して、人材育成に力を入れることが必要と考えているのですね。
小林: メンバーとの 「パートナーシップ」だけじゃ足りないとは思っていなくて、パートナーシップは絶対に大切にする必要があるんだけど、『ある風景』を改めて自分なりに咀嚼してみて考えたのは、そこだけを学び取るんじゃなくて、その前提に社会と積極的に関わり続ける強い意識をもった創設世代の存在というものを文章から透けて見えたわけですよ。
その人達が「作業所作ろう」、「授産施設で就労やろう」っていう部分は、社会との関わりを強く意識していたのだと感じ、大切だと思ったのですよ。
櫻井: 森内さんの文章の最後の方で「先人達の意思が、担い手を育てる」という文章が引用されていたんですが、彼のように優秀な人でさえ「(先代の)人材教育を引き継ぐことは難しい」と言っているような気がしました。つまり、小林さんもその先人にならなくてはいけないと考えているのですね。
社会とコミットメントする(つながる)
いろんな精神障害の政策の改善や社会改革などに吸収されて発信されるべきものが個人への攻撃や中傷として表出されている。精神障害の問題もこれらの問題も根っこは皆同じ所だから、どうにもしがたいし犯し難い課題を持っている。私達が長年悩んできた精神医療や福祉の改革も社会の諸問題に結びついているから、そもそも一つの世代で解決できる事ではなかったのかもしれない。いつかきっとの「いつか」は少し長いスパンで考えていこう。
『精神障害のある人の就労定着支援 – 当事者の希望からうまれた技法』
天野聖子 著/多摩棕櫚亭協会 編著(中央法規出版) より
小林: 『ある風景』の中では、文章として現れている部分が少なかったかなぁと思ったんだけれども、そもそも作業所が作られた経緯があって、それは創設世代の人達は社会にコミットメントして(つながって)いくというかソーシャルな存在として、例えば精神障害者が病院に収容されることに対してやっぱり真摯に関わって、作業所という新しい価値を作ったと私は理解しています。創設世代の人達は社会的におかしいと感じたことを「おかしい」とちゃんと言う人達だったんだと思う。
こういう人達が組織からいなくなった時に「おかしい」と言える人間がいないとまずい、必要な新しいサービスが出てこない。
棕櫚亭はいつも社会にコミットメントしてきたということでここまでやってきた気がします。そのために最初は無認可だったけど、どんどんどんどんそうやってコミットメントして、サポートして食える人を増やし、いろんな自分達の力や組織的にも力をつけてここまで来たと思います。社会福祉法人として組織化された今はどうやってある意味窮屈な現状を変えていくのが私達の大きな仕事でしょうね。
そういう意味では、私達が自身を成長させていく時に大切なのは、もう少しものごとを大きく捉えて、つまりフレームを広げ挑戦し社会にコミットメントしていく力で、私も含めて、まだまだ弱いなぁと感じるところです。
社会にどうやって棕櫚亭が関わっていくのか、コミットする力をどのように付けていくのか、考えていきたいと思うのですよ。
櫻井: そういえば、社会との接点といえば、1,000人規模のコンサートとかやってましたよね、「憂歌団」とか呼んで。行事をやってそこから運営費収入を得ていたとか、逞しさがありましたよね。
小林: 改めて考えた時、例えばコンサートを開くということの意義は、運営費稼ぎであったり、更に言えば、社会との接点つまり社会とのコミットを行なっていたということなんですよね。そういった感じのものを『ある風景』から学んで棕櫚亭らしさとして引き継いでいかないといけないなぁって思いますね。
櫻井: 小林さんの中で「コミットメント」という言葉が棕櫚亭成長へのキーワードになっているのですね。コミットメントを切り口に私自身の体験にひきつけて語るのならば、「社会からはじかれた自分」ということを思い出しました。
僕が大学の時に病気になって凄く人間不信に陥って被害妄想的なった時に「自分はこういう人間で、こういう考えだから」と先輩に10通くらい手紙を出したが1通も返ってこなかった。手紙を送ったにもかかわらず彼らが、言うならば社会が受け入れてくれなくて爆発しそうなエネルギーがあった。
その時は入院ってことになっちゃって「なんで入院させられるんだ!」という怒りもあったんです。
でも『ある風景』を読み、私が過去を振り返る意味を自分なりに考えた時になんで自分が病気になったかとか、なんで自分が入院しなきゃいけなかったのか、ということを気付かされました。つまり、その時の私は(小林さんが言うような福祉に)繋がらなかった人だったんだと思う。だから病気になってしまった。そしてそのまま(福祉に)繋がらなかったら一生涯わからなかったと思う、自分の病気とか。長かったけれども必要な時間だったのかもしれない。
自分自身のことや病気を知ることはここで言葉にするよりもかなり辛いことなのだけれども、その延長線上で棕櫚亭で仕事をするってこともできなかったと思う。かなり遠回りだったけど、自分を理解することで他の方の理解ができるようになった。自分の思い込みや思い違いがあるってことが実際に仕事をさせて頂いて、電話相談とかフリースペースに来る人達を通じて分かるようになってきたし、その溝を埋めることが、言葉であり、コミュニケーションなのだという気づきにつながっています。
そのことを敢えて伝える必要とは思わないんだけど、困っている人達がなんとなく、福祉に繋がってくれてよかったなぁと思っています。
そして職員となった今の僕も過去にははじかれた人かもしれないけれども、少しずつ引っ掛けていくという、そういう努力はこれからもしていかなきゃと思う。
小林: 櫻井さんが「社会からはじかれた」「辛い思い」は理解できます。でもコミットしていくことの必要を感じている私達の側から言うならば、もう一歩、二歩前にすすんで「本当は私達が出会わなければならない人達に出会う努力をしなければいけない」そしてそれが、社会にコミットするということだと思うということを私は言いたいのですよ。
櫻井: 確かに時間はかかってしまったが、棕櫚亭との出会いのなかから、いろんな人を知ることによって、社会から離れちゃった段階から、また新たに社会に戻されて社会の構成員としての生き方を見つけたんだと思うんですよね。
ちなみに、最近始めた「こども食堂」なんかのサポート事業も社会福祉法人として社会にコミット(貢献)したい流れの中で始めた事業ですかね?
小林: 最初は社会福祉法改正の中で社会福祉法人の社会貢献の義務化の話がでてきたので、棕櫚亭も何かやらなきゃという部分もあった。だけれども本来、社会福祉法が変わったからやるんじゃなくて関わってみたら、それより前にやっぱり社会のなかにある課題なわけだから、だったらそこに積極的に関わっていくというまず姿勢が私達には必要なんだと思い「子ども食堂」のサポートを始めたのですよ。社会福祉法人の社会貢献活動の義務化うんぬんは置いといて。
時代が変わっても – 普遍的なもの
AIやバイオテクノロジーが進化を遂げるなか、もしかしたら統合失調症の治療も大変化を遂げて、悲惨な精神病院の話は前世紀の遺物になるかもしれない。仮にそうだとしても、いつの時代も肝心なのは大きな渦中にいるたった一人のかけがえのない人を思う事であり、その人のありように通い合う心である。
『精神障害のある人の就労定着支援 – 当事者の希望からうまれた技法』
天野聖子 著/多摩棕櫚亭協会 編著(中央法規出版) より
櫻井: 山地さんが「10年後も(精神保健の)パイオニアでありたい」と書かれていたこと凄く印象的だったのですけども、そのパイオニア意識、ようするに開拓者であり改革者あり先人でありたいという意識を若い人にもってほしいと思っているのですね?
小林: 若い人もそうだけれども、まず私達棕櫚亭の経営陣が持たないと駄目だと思う。
何を耕すのか、何を開拓していくのかは社会の課題が見えてないといけないし積極的にそこに関わってなかったら課題が見えてこないから、パイオニアである為には社会に関心を持ちながら日々いなきゃいけない、それは凄く感じる。
福祉法制度上はいろいろ整ってきて、過去に比べれば精神障がい者にとって生きやすい社会になっていると思います。それでは日本が福祉的に充実してきたいえるのか?そこには疑問があって、私自身には実感が伴ってこないというのが本音です。結局、省庁の問題なんかも、障害者雇用促進法に定められた雇用率制度も以前に比べ拡充してきたにもかかわらず、行政庁が守っていなかったなど、露呈してしまった。ある意味実感を伴っていることだったんです。
そして、その実感の裏づけとして当事者の声に耳を傾け、その声を大切にしたいと思っているのです。例えば、SPJのような当事者活動からの声は大切だと思うのです。そういう当事者の声や力がこれから更に必要になってくると思います。
櫻井: その話を聞いて思い出したことがあります。工藤さんが書いていたのですが、障害者自立支援法ができた時に同じ生活支援を行なっている「なびぃ」と「Ⅰ(だいいち)」のサービスが似通っているから、地域活動センターとして一つに統合されるのではないかという危機感が法人にありました。その時に「それは困る」とメンバーさんが声を上げ、小林理事長と工藤さんとメンバーさんが市役所に行って話しをきいてもらった。その結果、それぞれ地活Ⅰ型とⅡ型として存続できました。確かにあの時のメンバーさんたちの声は大きかったと思います。ああいうことですかね。
いきなり自立支援法でサービスが変わるのはびっくりしてしまいましたけど。
小林: 福祉サービスの法律の改正って、今のような社会情勢の中で必要な通過儀礼だったのかもしれません。措置から契約への変更は、当時も思っていたけれども、でも今から振り返ってみても「自立支援法」ができたことって大きな改革だったなぁって感じるところだよね。
櫻井: でも、一方で法律が変わったところで変わらないことや場所がある。僕なんかは今も、棕櫚亭Ⅰにはのどかでゆったりできる昔からの雰囲気が残っている気がする。就労を目的をした場所ではないし、みんなが平日に行ってくつろげてる場所とか居場所として使っている所で、ある意味作業所時代のいい所を残している感じがする。あえて、棕櫚亭が残しているということなんでしょうね。
自立支援法によって、いろんなサービス形態ができ、選択の幅が増えたのはよいことだと思うのです。その一方で、社会的にみて経済性だとか効率性だとか強調される中で、人の尊厳なんていうと大げさだけど、安全に快適に過ごせる空間はいいなと思うんですけどね。この障がいの人達って一度経済社会からはじかれた辛さがあると思うので、まずはホッとできる気持ちを取り戻したいと思うのですよ。
形に残すこと – 出版することの意義について
小林: 棕櫚亭が社会福祉の活動を存続していくには、一定程度、制度にのらなくてはいけない事業規模になってきました。活動の継続性・連続性ということは、結果論ではなく法人としてきちんと取り組むべきことだと思います。そこは経営者として私は常に脳の片隅に持っています。それはメンバーと同様に、職員一人ひとりにも大切な生活があるということなのです。とはいえ、制度が変わろうと守らなければいけないものは、有形・無形、意識・無意識にいろんな断片として棕櫚亭のなかに残しているつもりです。
自分達の活動を「福祉サービス」という言葉で語ってしまったり、括ってしまうと、どうしても四角四面な印象が強くなって、自分達ができる事にリミッターを設定してしまうことがある。だから現場で働く職員には「支援の手法」よりも先に精神保健活動の意義や理念、そして棕櫚亭が思想性も含めて大切にしていることを意識して伝えなければいけないと感じている。実際、理念と実践を普段から言葉で結びつけ伝えていくようなことが、日々の忙しい活動の中で物理的(時間的)にも難しくなっている。支援の中身や意味づけって言葉にしづらいし、精神障がい者の方の支援って「言葉で行なうものだ」といいながらも、案外してこなかったなぁという反省が私にはあります。
櫻井: 社会福祉のあり方、つまりよいサービスを提供すれば棕櫚亭として事足りるのだという考え方ではないということなのですね。
小林:今回、前理事長の天野さんが『精神障害のある人の就労定着支援 – 当事者の希望からうまれた技法』執筆、出版されました。読ませていただいて、考えさせられたのは、「やっぱり語り継がなきゃいけない、人が育っていかなければいけない」と天野さんが思って、中にしまっていた言葉を全部紡ぎだしてくれたんじゃないかということです。とにかく、その熱量が凄い。理事長を引き継いだ私としてはプレッシャーを感じるほどです。
櫻井: 天野さんの書かれた文章で「諸問題を発信しても、これだけで全部を終われるかというとそうじゃない。これから、これをもとにしてやっていかなければならない」という凄い意欲を感じたのですけども、どのように次世代に繋げていくこととか、どうして過去を振り返るのかという問題を深く考えていかなきゃならないということですかね?
言葉にし切れてないってことはホントに僕らの未熟さもあるし、天野さんはいつも言ってたと思うんだけど「支援って言葉でやっていくんだよ」ってしつこいくらい言われてて、それは続けていかなければいけないし。この前に読んだ本で「社会ってコミュニケーションと言葉でできている」っていうようなことが書いてありました。だからそういう意味では言葉って凄く大事だし、そこは今後僕らに課せられたこと、発言していくことの大切さをこれからも考えていきたいと思いました。
小林: そうですね。これは森内さんも書いてくれたんですが「振り返ることができる歴史は組織にとって未来を作り出す財産だ」と書いてあるけど、まさに天野さんはそれをしてくれたんだろうね。天野さんが仕事を始めた精神病院の悲惨な歴史が今の私達の活動につながっていること、そしてその時遣り残したこと、思い残したことなど自分の負の部分をさらけ出して文字にしてくれている。「明るく、元気に、美しく!」を体現している天野さんもこんな歴史があり、思いがあり、「次どこへ行くのかしっかり自分達で考えなさい」ってバトンを渡されたのだと強く感じました。
天野さんも内省されていたように、私自身がどうしてここ(精神保健分野)で仕事をしているのか? どのような意義を見出しているのか今一度考え直すよい機会をいただいたと思っています。そして、平行して行なわなければいけない人材育成する上でとてもいい財産を残してくれたと感謝しています。
櫻井: 本当にありがたい財産ですよね。精神保健の関係者もさることながら、このような複雑多様化したいき難い社会の中で、ゆれながらも懸命に生きていく一人の人生の読み物としても刺激を受けます。読み手によっていろんなヒントが隠れていると思うので、ぜひ一般の方にも読んでいただきたいと思っています。ぜひ多くの方にお買い求めいただければと考えています。
小林: 最後になりましたが、この本という結晶は天野さんを中心に多くの人の下で生み出されています。形になったのは中央法規の柳川さん、アーガイルデザインの宮良さん、画家の満窪篤敬さん、そして、創設者世代の藤間陽子さん、寺田悦子さん、満窪順子さんのご尽力やアドバイスがあったからだと聞いております。感謝します。
本のあとがきに、感謝の一文を入れるのことが多いのですがかかれていません。それは、本に書かれたような大胆な行動家である一方、案外恥ずかしがり屋の面も強く持つ天野さんだからなのです。ですから、私 小林が現理事長として成り代わってこの場で改めてお礼申し上げます。
小林 櫻井 二人: (笑)
対談を終え…当事者スタッフ櫻井さんのコメント
『ある風景』も最後の対談を終え、『ある風景』に関わった人々皆様への感謝の念でいっぱいです。執筆いただいたかたは忙しい仕事の合間を縫って書いていただきました。ありがとうございました。
最後の小林理事長との対談はいろいろなことに話しがおよびました。
コミットメントというテレビCMでよく聞く言葉もつながっているという意味で使われていることが福祉の業界の特色をだしていると思います。CMでは誓約、確約などの意味で使われていたと思います。話は天野前理事長の本にも及びました。わたしも天野前理事長の若い頃からの人生の軌跡を読み涙がでました。挫折もあったけれどここまで棕櫚亭を大きな組織にした人生に感動しました。棕櫚亭が子供食堂への協力など社会福祉法人として果たしている役割を担っているのも誇りに感じました。
棕櫚亭の『ある風景』を語っていただいた方々につながる若い世代の人々が、この次はどんな “ある風景” を語ってくれるか楽しみです。
このサイトにアクセスし読んでいただいた皆様ありがとうございました。
編集: 多摩棕櫚亭協会 「ある風景」 企画委員会
購入は ↓
『精神障害のある人の就労定着支援 – 当事者の希望からうまれた技法』
天野聖子 著/多摩棕櫚亭協会 編著(中央法規出版)
もくじ
- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❶ “はじまりにあたって” – 多摩棕櫚亭協会「ある風景」企画委員会
2018年8月17日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❷ “作業所は「メンバー抜きにはメンバーのことを決めてはいけない」ことを教えてくれた場であった” – 荒木 浩
2018年9月7日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❸ “そこにあるすべてをメンバーとともに” – 伊藤 祐子
2018年9月28日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❹ “失われた〈共同作業所〉が、もしかしたら世界のトレンドになるかもしれないというウソのようなホントの話” – NPO法人多摩在宅支援センター円 添田 雅宏(棕櫚亭OB)
2018年10月19日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❺ “悩みが許された時間と空間がそこにはあった” – 吉本 佳弘
2018年11月16日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❻ “Keywordは、「就労」「ピア」「生活」「食事」…かな。” – 森園 寿世
2018年12月7日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❼ “対談編 – 『ある風景』から見えてきたこと” – 理事長 – 小林 由美子 × ピアスタッフ – 櫻井 博
2018年12月28日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❽ “組織にとっての過去の意味” – 株式会社エムエフケイ 森内 勝己(棕櫚亭OB)
2019年1月18日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❾ “始まりはボランティア” – 工藤 由美子
2019年2月8日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ❿ “贅沢な時間をすごせた時代 切り取ることができない大切な時間” – 川田 俊也
2019年3月8日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ⑪ “十年先に向かって ― 回想 山地 圭子”
2019年4月5日(金)公開- 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ⑫ “未来へのヒント – 高橋 しのぶ”
2019年4月26日(金)公開- 【最終回】 『ある風景 〜共同作業所〈棕櫚亭〉を、私たちが総括する。』
Part ⑬ “対談編 – 過去を振り返って未来へ – 小林 由美子 × 櫻井 博”
2019年5月31日(金)公開
(このページ)


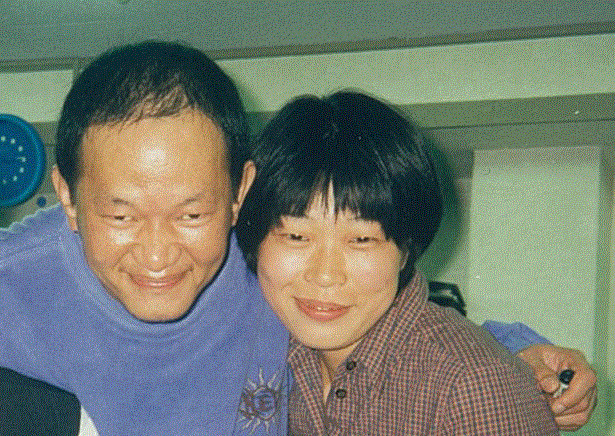
 福祉のあり方が大きく変わり、制度への疑問や戸惑いが残る中ではありますが、こんな時だからこそ課題や目指すべき方向性をだして私は頑張っていきたいです。発想を変えることも迫られるかもしれませんが、一人一人が役割とミッションを自覚して「理念」を追い求めていこうと思います。職員同士とのコミュニケーションを活発にし、モチベーションを高くすれば超えていける、手に入るものも多くなるはずではないか思う。
福祉のあり方が大きく変わり、制度への疑問や戸惑いが残る中ではありますが、こんな時だからこそ課題や目指すべき方向性をだして私は頑張っていきたいです。発想を変えることも迫られるかもしれませんが、一人一人が役割とミッションを自覚して「理念」を追い求めていこうと思います。職員同士とのコミュニケーションを活発にし、モチベーションを高くすれば超えていける、手に入るものも多くなるはずではないか思う。 ということを率直にぶつけていました。「そこまで言うのか?」というのもあったかもしれません。メンバーさん達からは「いやいや違うだろう!」という押しかえしもたくさんありました。結果的に僕が間違った態度も多く、素直に「ごめんなさい」と謝ることもたくさんありました。この年になっても人に謝るということができることは大切な財産だと思います。
ということを率直にぶつけていました。「そこまで言うのか?」というのもあったかもしれません。メンバーさん達からは「いやいや違うだろう!」という押しかえしもたくさんありました。結果的に僕が間違った態度も多く、素直に「ごめんなさい」と謝ることもたくさんありました。この年になっても人に謝るということができることは大切な財産だと思います。 時には泣いて。そんな日常風景が流れていき、この作業所一部に溶け込んだ時に、メンバーさんの「いいとこ探し」をしている自分がいることに気がついていました。棕櫚亭Ⅰ(だいいち)の「ワンピース」になったみたいな感じです。
時には泣いて。そんな日常風景が流れていき、この作業所一部に溶け込んだ時に、メンバーさんの「いいとこ探し」をしている自分がいることに気がついていました。棕櫚亭Ⅰ(だいいち)の「ワンピース」になったみたいな感じです。

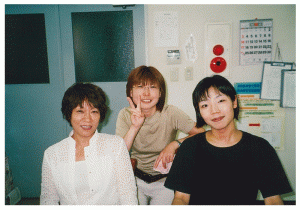 ほとんどが私より年上の男性メンバーさん方で、喧嘩もあれば、ちょっと女性が聞き辛い話(今で言うセクハラ 話?)もありました。働くことを目指すといっても、作業が終わるとマージャンを毎日のようにやっていました(近所のおじさんたちの集まるサロン!?)。でも、麻雀牌を捨てながら、誰かが「家族とうまくいっていない、そもそも自分の病気のせいで、家族に大変な思いをさせてしまった、だからいま寂しくても仕方がない」なんて話し出すと、そうだよな…… Aさんは大変だよなぁと相槌を打ちながら聞いてあげています。
ほとんどが私より年上の男性メンバーさん方で、喧嘩もあれば、ちょっと女性が聞き辛い話(今で言うセクハラ 話?)もありました。働くことを目指すといっても、作業が終わるとマージャンを毎日のようにやっていました(近所のおじさんたちの集まるサロン!?)。でも、麻雀牌を捨てながら、誰かが「家族とうまくいっていない、そもそも自分の病気のせいで、家族に大変な思いをさせてしまった、だからいま寂しくても仕方がない」なんて話し出すと、そうだよな…… Aさんは大変だよなぁと相槌を打ちながら聞いてあげています。 考えようと、障害福祉関連のニュースや、文献をミーティングなどで紹介してくれていた。
考えようと、障害福祉関連のニュースや、文献をミーティングなどで紹介してくれていた。